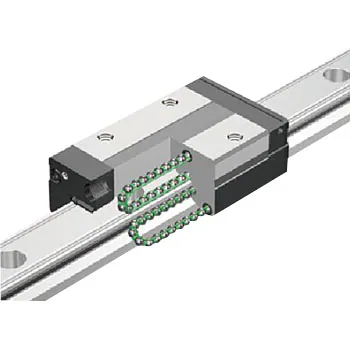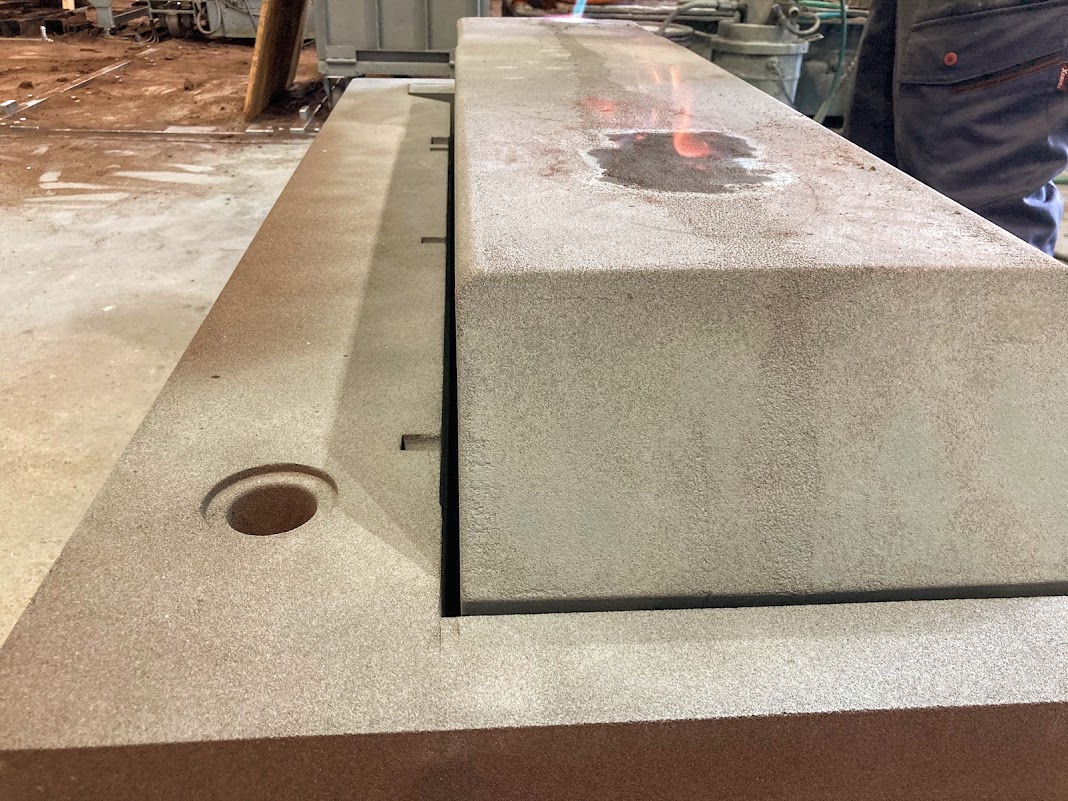このQ&Aは役に立ちましたか?
二重絶縁構造とは?電気用品安全法について知ろう
2006/03/17 10:16
- 電気用品安全法の中には、「二重絶縁構造」という言葉があります。一般的にはよく分かりにくいですが、実はとても重要な概念です。この記事では、二重絶縁構造について詳しく解説します。
- 二重絶縁構造は、電子機器の安全性を高めるために導入された仕組みです。一般的には絶縁材料を2重に使うことで、電気的に隔離された状態を作り出します。このような構造は、万が一絶縁壊れが起こったとしても二重の安全性を確保することが可能です。
- 二重絶縁構造は、電気用品の充電部からの距離や絶縁物の厚みといった具体的な要素に関係しているわけではありません。重要なのは、絶縁材料が2重に使用されていることです。二重絶縁構造は、電気用品の安全性を高めるために広く採用されており、安全基準を満たしている製品は二重絶縁表示がされています。
二重絶縁構造
電気用品安全法の中に、二重絶縁構造というのが出てきます。
何となく、分かる様な気がするのですが、もう一つよく分かりません。
どの様な構造なのか?
充電部からの距離?
絶縁物の厚み?
など・・・
何か具体的に分かる資料は無いでしょうか?
アドバイスお願いします。
なにぶん素人なので、よく分かりません。
よろしくお願いします。
関連するEMIDAS技術情報
回答 (4件中 1~4件目)
こんにちは。
この辺りは御覧になりましたか?↓
http://homepage3.nifty.com/tsato/terms/iec950-table2h.html
上のURLの表を例で説明しますと、
仮に汚染度3で、DC7kVの場合、最小空間距離は17.5mmとなります。
この17.5mmの中に2枚の絶縁物を入れます。
入れる絶縁物は、材質により厚みが異なります。
通常は各材質(樹脂等)に「破壊電圧」がありますので、
それに安全マージンを加味した厚さを指定します。
安全マージンは設計する側の社内規定で決めていると思いますが、
うちの会社の場合、3倍見ています。
(絶縁物の破壊電圧が厚さ1mm辺り30kVの場合、耐圧は10kV)
↓破壊電圧を明記したサイトの例です。
http://www.mmm.co.jp/electro/tape/main_top.html
http://www2s.biglobe.ne.jp/~kesaomu/b01.html
等
ご参考までに。
このQ&Aは役に立ちましたか?
この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。
回答では、なくてすみませんけど
回答(2)の akrさんのコメントで
「二枚ともダメになってしまったらどうしようもないですけどね。」ですが
そういう時にこそ、危険性のある所に「こういう事があったらこうする」と注意ラベルを貼るとか説明書に記載する事が、長い目で見たら何人かの命や被害が減るかもしれません。
説明書なんか見ないよ~という人が大多数でも、注意喚起行為で一人でも救われれば良いのではないでしょうか!
二重絶縁構造の発想も方向性は同じだと思います。
akrさん、引用してすみません。悪意は無いです m(__)m
二重絶縁構造とは、基礎絶縁(機能絶縁)+保護絶縁の二つからなります。
基礎絶縁とは、感電に対する最低限必要な絶縁です。
過電圧などの要因により、この絶縁が破壊された場合、感電する危険があります。
保護絶縁とは、この基礎絶縁が破壊された場合の、感電の保護目的とした絶縁です。
このことから、保護絶縁は基礎絶縁とは独立して設ける必要があります。
分かりやすく説明すると、絶縁物の「厚み」ではなく、重ねる枚数と考えてください。
一枚ではなく、二枚重ねると、一枚目に亀裂があったとしても、絶縁機能が保てることになります。
二枚ともダメになってしまったらどうしようもないですけどね。
簡単にいえば、電動グラインダー(100V)を考えてください
昔はほとんど本体が金属で覆われていた物しか
無かったですヨネ
良く工事現場で煩雑な使用をしていたらコードが断線したり
スイッチの所で不良が起きたりして、これが「漏電」「感電」に
つながり易くなります。金属は電気の良導体ですから。
それを防止する対策として(軽量化も含め)本体をプラスチックや
樹脂類にして上記のような事故を防止することを可能にしたという
事で近年、急速に2重絶縁構造として普及しています。
専門的にはもっと詳しい変化・内容があるかも知れませんが
私はこういう風に理解しています。